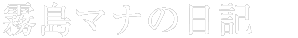-冷めた血が私を苦しめる-
冷めた血が私を苦しめる
ケイタが死んだ。殺されたのだ。
ずっと前から彼が脱走を企てているのは知っていた。
私たちが冗談でトライデントに乗って逃げたら誰にも捕まえられない、
と言っていたのを本気にしたのだ。
要領の悪いケイタは、上官はもとより古参の同僚からも毎日のように殴られ、
いつも逃げ出すことばかり考えていた。
トライデントとは、戦自が極秘裡に開発した「陸上軽巡洋艦」だ。
熱核融合炉を内蔵し、無尽蔵とも言える電力を駆使した強力な武装は
今のところ他に匹敵するものがない。
そして、私たちはこの恐るべき兵器を操るために集められた少年兵だった。
部品だった、と言う方が正確かも知れない。
今にして思えば、あのとき、思い詰めた顔で計画を語る彼に、
私は絶対に無理だからやめた方がいい、と
通り一遍のことを言うだけで、真剣に説得しなかった。
ケイタが本当にあの計画を実行するとは思っていなかったから。
なにしろその「計画」によれば、私も脱走に加わる事になっていたのだ。
しかもその内容たるや、南の島まで逃げ延びて仲良く暮らそう、といった幼稚なものだ。
普通に考えたら、本気だとは思えないのも道理だろう。
しかし、彼はまぎれもなく本気だった。
彼のその後の行動がそれを証明しているというだけではない。
あの表情、あの声。訥々と、しかし、しっかりと私の目を見て話していた彼が、
「どうせ本気じゃない」などと、なぜ思ってしまったのか。
いや、本当は分かっていたのだ。
分かっていてそのことから目をそむけた。直視できなかった。
その後私は諜報部に転属となり、さすがにケイタの脱走計画も
沙汰止みになったろうと思っていた。
少なくとも、私の意識に上ることはなくなっていた。
しかし、彼は一人で実行したのだった。
最後に彼を見たときは、戦自病院で昏睡状態となっていた。
捕らえられた際に負傷したのだという。
無残な姿だが、私は、このまま当分目覚めなければ、
あるいは彼も命を保つことができるかもしれない、と考えたものだ。
もし目覚めなければ、トライデントの秘密が外部に漏れることもない。
表向きは訓練中の事故ということにしてなんとか彼を生かしておいて欲しい。
私はそう願った。
しかし、彼は殺された。使えない部品として処分されたのだ。
彼が死の直前に昏睡から覚め、「脱走は自分一人で決めたこと。仲間は関係ない」だとか、
あるいは逆に「もう一度だけ仲間に会いたい」などと言ったかどうかは分からない。
私はただ「彼は死んだ」とだけ聞かされた。
だから、「殺された」というのも実のところ確証はない。
私の中の冷めた血が、そう告げるのみだ。
うだるような暑さだ。
彼の亡骸がどうなったか気にならないではない。
が、気がつくとあまり考えないようにしている自分を発見する。
恐らくは病院の関係者によって荼毘に付され、無縁仏として葬られたのだろう。
もともとトライデントのパイロット候補には天涯孤独の者が集められている。
納骨といった儀式めいたことが行われたのかさえ定かではないが、
ともかくも骨をどこかに安置した後は、
もう彼のことを気にかける人間はこの世に誰一人いないのかも知れない。
かく言う私も、彼の墓を探し出して花の一束でも手向けようという気持ちは無い。
現実的に不可能だという理由もあるが、
そうしなければならない、という強い情念が涌かないのだ。
なぜこんなにも冷たいのだろう、私の心は。
そのことが私を恐怖させ、ケイタの死そのものよりも数倍悲しませる。
唯物主義者は、人間とは物質に過ぎぬと言う。
それでは、こうやってとりとめもなく彷徨う私の心も、
その物質の作用に過ぎないのだろうか。
それもよかろう。たとえ「この苦しみは神の与え給うた罰だ」と考えたとしても、
それによって罪が軽くなるわけでもないのだから。
それとも、苦しいというのも実は錯覚なのか。
「こういうとき、人は苦悩するものだ」と教えられてきたから
その通りにしているだけなのだろうか。
本当は、このように千々に乱れること、それ自体が苦しみなのだ。
痛覚とは神経を伝わる電気信号に過ぎないからといって、
腕にナイフを突き立てて平気な人などいない。
理屈では分かっているつもりでも、自分の身に降りかかれば、
圧倒的な力で私たちの全身全霊を支配する。
それが痛みというものだ。苦しみというものだ。
だが、それも時とともに薄れ行き、
消え去りはしないまでも、いつか、ほとんどその存在に気がつかないようになる。
私のような冷たい人間にはなおさらだ。現に、今、この瞬間でさえ、
ケイタのことよりむしろ自分のことを嘆いている私のような。
こんなにも心醜い私。
こんなにも冷たい私。
そして、ある種の自己嫌悪を覚えつつも、
心の奥底では決して自分を見捨ててはいない私。
要するに自分がかわいい私。
これが私という人間なのだ。
そこかしこでうるさいほどにクマゼミが鳴いている。
乾いた歩道には私自身の濃い影が落ちている。
ほとんど風がなく、むせ返るような熱い空気はじっとりとその場にとどまったままだ。
私は立ちのぼる入道雲を見上げ、
「さようなら、ケイタ」
と呟いた。
(了)