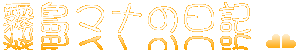-キスの味なんてわからない-
墜落
「折角の再会だっていうのに、マナの奴、何が気にくわないんだ」
ムサシはマナの態度に少し苛立っていた。
第三新東京市、午前一時。
新歌舞伎町には色とりどりのネオンが輝き、まさしく不夜城のような趣である。
喫茶室ルノアールの空いた店内の窓側の席に、若い男女が向かい合って座っていた。
男は痩せてはいるもののがっしりとした体つき。深緑色のツナギを着ている。
女の方はノースリーブの白いブラウスにオレンジのチェックのミニスカートだ。
二人ともすらりと背が高く大人びて見えるが、良く見るとその顔つきは
男女というよりは少年少女と呼ぶ方がふさわしい。
「これからどうするの?」
少女が尋ねる。
「芦ノ湖の水面の下に機体を隠してある。
コックピットをケイタに任せてるのがちょっと心配だけどな。
マナ、お前が来れば今これから日本を脱出だ」
浅黒い肌の少年、ムサシは、マナと呼ばれた少女の手を取って答えた。
「だめよ……」
マナが少年の手を振りほどく。が、その態度は邪険というほどでもない。
一緒に行きたいのはやまやまだがどうしても行けない理由がある、といった様子だ。
「なぜだ?」
「任務があるもん……」
「任務がなんだよ。ここから逃げ出しちまえばそんなものもう関係ないじゃないか」
「だめなものはだめなの」
「まさかお前、あのシンジとかいう野郎と……」
「そんなはずないでしょ! ムサシのバカっ」
そう、マナがシンジとかいう少年に近づいているのは単なる任務の筈。
色仕掛けに近いことまでやっていると聞かされたときは
さすがに嫉妬心が涌かないでもなかったが、マナがそんな話をするということは、
この俺を本当の恋人と認めているからこそに違いない、ムサシはそう考えた。
この少年は、何事も前向きに考える性格なのだ。
もっともその前向きに考えた結果が、「脱走」というのだから皮肉という他はない。
彼らは、戦自、戦略自衛隊が極秘裏に開発した陸上軽巡洋艦「トライデント」のパイロット候補生だ。
一時は理想に燃えて戦自に入隊したムサシ、マナ、ケイタだったが、
トライデントの部品として扱われる日々に嫌気がさし、
今はもう何も信じられなくなっていた。三人の仲間以外は。
「お前に振られるのは二度目だな」
ムサシは軽く溜息混じりに言った。
「そうだっけ」
「あの時だよ、ほら、例の墜落事故の時」
「ああ、あの時ね……」
ムサシの「事故」という言葉に、マナはなぜか一瞬ハッとしたようだった。
………
……
…
山梨県北部上空、午後二時。
明らかに異常な飛び方をする一機のVTOLがあった。
夥しい量の白い煙を吐きながら、右へ、右へと旋回しつつ急激に高度を下げている。
「おかしい、出力がどんどん下がってるよ!」
ケイタが叫ぶ。
「うろたえるな! 燃料残量は?」
なんとか機体を立て直そうと操縦桿を握りしめるムサシ。
「まだ800Kg以上あるよ!」
「よし、それじゃ燃料供給を手動に切り替えてみろ!」
「了解!」
「……だめだ! 計器では両エンジンに燃料が行ってるはずなのに!」
「マナ、救難信号を発信!」
「了解! メーデー、メーデー、こちら戦自練習機0021号、故障により墜落中 」
マナは無線機に向かってそう叫びつつ、
如何にも緊急時に押せと言わんばかりに黄色と黒で縁取られたボタンを押した。
「軟着陸は不可能だ! パラシュート用意!」
ムサシがそう叫ぶと、マナは座席の下に置かれたパラシュートを三つ引っ張り出し、
二人の少年、ケイタとムサシに渡した。
「ケイタ、お前から脱出しろ」
「う、うん……」
訓練を受けているとはいえ、パイロット達にとってパラシュート降下は専門ではない。
多少逡巡するのも無理からぬ事だ。
「大丈夫だ」
ムサシはケイタのハーネスストラップを締め直してやると、背中を叩いた。
「コードが絡まないようにちゃんとアーチの姿勢でね……」
マナがケイタの手を取り、心配そうに言う。
「わ、わかった……」
「降りたらすぐに発煙筒を焚け。俺とマナはそれを目標に合流する」
発煙筒はパラシュートとセットになっている。
「了解……」
「よし、いけ!」
ケイタは意外にも思い切りよく飛び降りていった。
「ムサシ、あのね……」
マナがなにやらいわくありげに言いかけるが、
「次はお前だ、マナ。何をしている、急げ!」
ムサシはそれには耳を貸さず、降下をせかした。
「DZ(Drop Zone, 降下範囲)が広がると集合がめんどうだ、急げ!」
「うん、ムサシも気をつけてね」
マナが降下。
ムサシもほんの数秒後に飛び降りる。
強烈な風圧。眼下には延々と広がる樹海。
セカンドインパクト後人口が激減したこの地域は、まるで原生林のように鬱蒼と木々が茂っているのだ。
開傘するとグッと身体が持ち上げられるような感覚とともに急速に減速するが、
いかんせん低高度からのイグジットだ。みるみる間に地表が迫る。
ガサガサッ、ザザーッ
小枝が折れる音とともに全身を激しく引っ掻かれたような痛みが襲う。
「大丈夫か、マナ?」
「うん、平気。ムサシは?」
「何ともないみたいだ。よし、ケイタはあっちだな」
どうにか着地したムサシとマナは先に降りたケイタと合流すべく、
機が最後に向いていた方向の逆、北へと歩き始めた。
むっとするような湿った南風が背後から吹き抜ける。
練習機のエンジン出力が低下した時点で、ムサシはほぼ無意識に風上へ機首を向けていた。
固定翼機ではそうやって少しでも揚力を稼ぐのがセオリーなのだ。
もちろん、VTOLでは何の意味もない。
初等練習機のマニュアルに書いてあったことを律儀に実践してしまった自分にムサシは苦笑した。
これほど嫌っている戦自に、どっぷり漬かってしまっていることに。
しばらく進むと、数百メートル先に赤い煙が見え始めた。ケイタが焚いた発煙筒に違いない。
ジャングル並の状況なので多少時間がかかるだろうが、それでも三十分以内には合流できるはずだ。