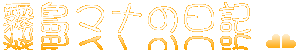-キスの味なんてわからない-
Kiss I
燃え尽きた発煙筒を前にムサシとマナは途方に暮れていた。
ケイタがいない。
「あのヤロウ……」
ムサシがギリギリと奥歯を噛み合わせる。
「どうしよう、探しに行こうか?」
ムサシの飛行服の袖をつかんで言うマナ。
「いや、俺たちがここから動いたらそれこそ合流できなくなるぞ。
奴が戻ってくるのを待とう」
ムサシはそう言うとミズナラの大木の根元に腰を下ろした。
「あのバカ、どこに行きやがった」
「……トイレかな?」
「この雑木林の中でトイレもへったくれもあるかよ!
そこらの木陰で用を足せばいいじゃないか」
マナは、ムサシのケイタに対する怒りが自分にまで飛び火したのを見て、
「えぇ、いやだなぁ」
とはぐらかした。
「だいたい、整備班の連中は何をやってるんだ。
いつも安全な地上にいながら、俺たちが命を預ける機体の整備を怠りやがって」
訓練生のくせにまるで歴戦の古兵のように整備の連中をなじるムサシ。
ただし、彼とて理由もなく整備兵らに責任を押しつけているわけではない。
操縦ミスではなかった。あれは機体の整備不良だ、そういう確信はあった。
「ケイタもケイタだ。集合地点から移動するなんて。ったく、どいつもこいつも……」
ふと、横を見るとマナは浮かぬ顔をしている。
「……すまない。少し愚痴が過ぎたな。
俺も発煙筒を焚いたらその場から動くな、と指示するのを忘れていた」
そんなこと、指示されなくても誰だって分かることだろう、
と思いながらも、ムサシはどうにか自分をなだめた。
「まぁ、横田基地は目と鼻の先だ。
すぐに救援ヘリが来るさ。それまでのんびり待つとするか」
ところが、いくら待ってもケイタは戻らず、救援ヘリもやって来なかった。
あたりは少しずつ暗くなりかけている。
「遅いっ! 連中は一体何してやがるんだ!」
ムサシが憤懣やるかたない様子で言う。
「うん、遅いね、ケイタ」
マナが話を合わせると、
「ケイタもだが、救助が来るのが遅すぎる。
ひょっとするとケイタだけ先に救助されたのかとも思ったが、違うようだな。
――とすると、ケイタの身になにか起こったか」
「どうしよう……」
「いずれにしろ、基地では俺たちが遭難したのを把握していないということだ。妙だな」
「レーダーに細工してあって私たちの機は映らないんだって。秘密訓練だから」
彼らが所属する特別VTOL大隊は戦自の中でも極秘扱いの“存在しない部隊”だ。
一般の戦自部隊とは訓練空域も異なるために、偶然発見・救助されるということは期待できない。
「それにしても、大隊の特別管制室では墜落に気づいている筈だ。
大方、もう死んじまってるから探しても無駄、とでも思ってるんだろう。
俺たちの命なんて安いものだとは知っていたが、これほどまでとはな。
いくら安いとは言っても、ただ死なれては連中も損だろうに」
『連中』とは無論、特別VTOL大隊上層部のことである。
(実質はVTOLではなくトライデントを運用する部隊なのだが、
新兵器であるそれの存在を秘匿する目的で、専ら特別VTOL大隊と称されている。
また、訓練は全てトライデントと操縦感覚の似ているVTOL機で行われる)
話の矛先がお偉いさん達へ向かい始めると、マナはますます柳眉を曇らせる。
「そんなことないよ。もうすぐ救助が来るよ、きっと」
マナの「上層部批判は止めて」と言わんばかりの口吻に、ムサシは少しカチンときて、
「ふん、機を落っことすほど出来の悪い俺たちなんかには見切りをつけて、
新しい候補生を仕入れるのかも知れないぜ。孤児はいくらでもいるからな」
と言い放った。トライデントのパイロット候補が孤児ばかりなのは、
他ならぬ自分たちが一番よく知っていることだった。
「そうだ、いっそのこと、ケイタが戻ってきたら三人で、
いや、今すぐ二人でもいい、このまま逃げちまおう……」
そう言いかけたムサシの口を、突然マナの柔らかい唇が塞いだ。
「…………!」
息が止まる。濡れた口腔粘膜が擦れ合う感触。
何故? 一瞬よぎる疑問。しかし、その問いを発した脳髄は、すぐに麻痺し始める。
ムサシはそのままマナを抱きしめた。
直後、
ガサッ
下草を踏む音が聞こえた。
ハッと我に返ったムサシが音のした方を振り向くと、
両手いっぱいにレーションやメディカルセットを抱えたケイタが立っていた。