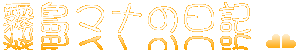-キスの味なんてわからない-
Kiss II
「遅かったじゃないか、何してたんだ?」
少しバツの悪そうにムサシが言う。
ケイタは約束の集合ポイントから勝手に離れたのだ。本当なら殴り合いになっていたかも知れない。
が、マナとのキスを見られた後ろめたさから、ムサシはほんの少し弱気になっていた。
「機体が……」
ケイタは言いかけて喉を詰まらせ、十秒以上も黙りこんだ後にようやく話し始めた。
「ムサシたちが飛び降りた後、機体が急旋回して僕の落下地点のすぐそばに落ちたんだ。
だから、食い物とか通信機があると思って」
「すぐそば? すぐそばだと!? お前、すぐそばまで行って帰るのにどれだけかかってんだよ!」
一度は怒りを収めようとしたムサシだったが、
ケイタの口べたも相俟って、いつもの癇癪を爆発させかけた。
「ごめん。思ったより地形が複雑で歩きにくくて……」
ケイタがもともと泣きそうな顔をさらに泣きそうにしている。
富士の裾野の地形の歩きにくさは、ムサシも今しがた身を以て体験したところである。
溶岩が固まって出来たこの地面は想像以上に歩行困難で、遭難者が多く出るのも頷ける。
「それに、こんなにいっぱいあったよ、食い物」
無邪気そうに"戦利品"を掲げてみせるケイタ。
「…………。そうか、いや、俺も怒鳴って済まなかった。食い物なんかよく燃えずに残ってたな」
ムサシの癇癪玉はどうやら湿気っていたようで、発火には至らなかった。
「うん、機体はバラバラだったけど、燃えてはいなかったよ」
とケイタ。食料は、もともと非常食として積んであった物だ。
「じゃ、さ、食べよ、パックメシ」
無理やり明るい声を出すマナ。パックメシとはレトルト食品の戦自での通称だ。
あまり女の子らしい言葉遣いではないが、みんなそう呼んでいるので仕方がない。
「うん」
ケイタは幼い子供のように返事をすると、さっそく加熱袋にレトルトを突っ込んだ。
化学反応によって熱を発生させ、火を使わずに暖めることが出来るのだ。
もっとも、今は火をおこして救援機に発見して欲しいところだが、
ケイタによると、マッチもライターも見つからなかったのだそうだ。
20分後。
レーションはすっかり暖まった。
箸やスプーンはないので、袋の両端を親指とその他の指とで押さえ、傾けながら口を付けて啜る。
なんともへんてこな食べ方だが、これが戦自での流儀だ。
「どうした、マナ。浮かない顔して。お前が食おうって言い出したんだぞ」
マナがほとんど食べていないのに気づいてムサシが声をかける。
「う、うん。あんまりお腹空いてなかったかも」
奥歯に物が挟まったような言い方のマナ。
「なんだよ、まさか、この非常時にダイエットってわけじゃあるまいな」
「あ、そ、そのまさかなの。ダイエット中なんだ」
しどろもどろになりながらマナが答える。
いくらダイエット中でも、小半日何も口に入れていないのだ。
おかしい、と考えながらムサシは急に思い当たった。さっきのキスだ。
実はあれが自分にとって初めてのキスだったのだが、マナもそうに違いない。
さてはあれが気になってメシも喉を通らないのだ。
やはり、さっきの感触が口にまとわりついているのだろうか。自分と同じように……
ムサシが想像を膨らませていると、遠くから聞き慣れた爆音が聞こえてきた。
「ヘリだ!」
ムサシとケイタはほぼ同時に同じ方向を指差しながら叫んだ。
一路基地へと向かう救助ヘリ。
兵員輸送用を兼ねたその機体のキャビンは広く、一個分隊を収容できるほどだ。
隅っこで小さくなっているケイタを尻目に、ムサシはマナの隣に腰掛けた。
ようやく救助されて一件落着だというのに、マナは、なぜか憂鬱そうな顔をしている。
やはり、さっきのキスのことを、後悔? ――しているのだろうか。
そう思うと居ても立ってもいられず、
「マナ、俺は……」
ムサシが、マナの手を握り、想いを打ち明けようとしたその瞬間、
「ごめんなさい」
マナはムサシに握られた手を引っ込めた。
愕然とするムサシに向かって、
「さっきのことは忘れて。お願い……」
うつむき加減にそう言うマナの瞳は赤く充血している。
ただ事ではない雰囲気に、ムサシはそれ以上詰め寄る気迫を失ってしまったのだった。
………
……
…
物語は深夜の喫茶室ルノアールに戻る。
ムサシが「マナに振られたのは二度目だ」と言った、その一度目はかくの如くであった。
僅か半年前のことだが、年若い二人にとっては随分古い思い出のように感じられた。
「任務ってお前」
ムサシは、マナが口にした「任務」と言う言葉を頭の中で反芻していて、突如閃いた。
「あれも任務だったのか?」
あれとは例の墜落事故のことだ。いや、事故ではなく仕組まれた事件と言うべきか。
「うん、ごめんね……」
マナはあっさりと認めた。ただし、目に涙を浮かべながら。
「俺とケイタに脱走の意思があるかどうか確かめるためか?」
「ええ。私の諜報部への異動が認められる条件でもあったの」
マナが頷くと、涙が一粒こぼれた。
仲間を監視させるなんて、連中、相変わらずひでぇことしやがる。
ムサシは心の中でそう言いながら憤った。
恐らく、ムサシとケイタの脱走計画を炙り出すためというよりは、
マナの諜報員としての適性を調べるのが目的だったのだろう。
思えば、あの後、形ばかりの事故調査が行われたのみで、
操縦ミスを疑われることもなかったのはそのためだったわけだ。
それにしても、資材の乏しい中で、貴重なVTOL1機を潰してまでテストするとは、
戦自は一体、マナになにをやらせているのだろう。
ムサシは、マナが背負っている物の巨大さを垣間見た気がして、背筋が冷たくなった。
「泣かないでくれ、マナ。謝らなくてはいけないのは俺の方だ。
つまり、あのとき、お前は隠しマイクを付けられていたんだな?
そうとも知らずにお偉いさん達の悪口を言いまくって、あまつさえ脱走の相談までして。
なんてバカなんだ、俺は」
そこまで考えて、突然思い当たった。そうか、そうだったのか。
「あのキスも……」
ムサシは、彼らしくもなく語尾を濁らせつつ言った。
「うん。他に黙ってもらう方法が思いつかなかったの」
「そうだったのか……。すまん……」
「ううん、本当のこと言えないのは辛かったけど、ムサシとキスできてうれしかったよ」
マナは急に涙を拭い、笑顔を作りながら言った。
「俺もだ」
二人は、しばし見つめ合っていた。
数分後。
「そうか、そりゃメシも喉を通らねぇよな。
食いしん坊のお前が、パックメシ食わないからおかしいと思ったぜ」
マナがようやく明るさを取り戻したようなので、ムサシが軽口を叩く。
「あ、あれは違うの」
不意に首を横に振るマナ。
「違うって何が?」
「あのときごはん食べなかったのはね、虫歯のせいなの」
「はぁ?」
頓狂な声を出すムサシ。
「もう、奥歯が痛くって痛くって。VTOLの震動はガンガン響くし、
落下傘降下のときなんかちょっとでも口を開くと風がすーすーして最悪だったよ」
「なんだ。離陸前からやたら神妙そうな顔してたのは任務のせいじゃなくて虫歯のせいかよ」
「半分くらいは、そうかな」
やれやれ。
「しかし、虫歯、今はもう直ったのか?」
「うん。ってか、乳歯だったからね、すぽっと抜けて万事OK♪」
「ったく。なにが『すぽっと』だよ。これうつしたのはお前か」
「へ? ムサシも虫歯なの?」
「ああ」
「でも、虫歯ってうつったりするかなぁ」
「ばかやろう、虫歯菌ってのはあれでうつるんだよ」
「あれって?」
「あれはあれだよ」
「何?」
「これ」
ムサシは、そう言いながら身を乗り出してマナに唇を重ねた。
一瞬見開いた目を徐々に閉じるマナ。熱い吐息が鼻にかかる。
「……………………」
「ムサシ、わたし……」
唇が離れると同時にマナが何か言いかけたが、
ムサシは、テーブルの脇に置かれた伝票を手に取り、くるりと背を向けると、
「お返しだ」
と呟やき、去っていった。
(了)