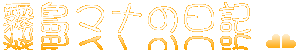-外伝(2)-
番外編:冬月・心の記録
確かあれは2月14日の午後だった。私はクリーニング屋からの帰り道、
一人荷物を抱え、ゼイゼイと息を切らしながら歩いていた。
この歳で独り身であることの侘びしさが身にしみる。
加えて、世間ではバレンタインデーだのなんだのと浮かれている。
まったく、この暑苦しい気候でバレンタインなんぞ、風情も何もあったものではない。
それを、近頃の若い者ときたら。
いや、いかん、いかん。昔を懐かしみ今を厭うのは思想の堕落の兆候だ。
そう思いながらも懐古の情は醒めやらず、いつしか、
私の脳裏には小雪の舞う2000年のバレンタインデーの記憶が鮮やかに甦りつつあった。
………
……
…
盆地である京都の冬は底冷えのする寒さだ。
「冬月先生。これ、どうぞ……」
廊下で、碇ユイは私にチョコレートを差し出した。吐く息が白い。
「ああ、すまんな、碇君」
受け取る際、ためらいつつそっと手に触れると、彼女は無言で涼やかな瞳を伏せた。
分かっていた。彼女の心の中に私の入り込む隙などない、と。
あのチョコレートは、単に義理でくれたのに相違ない。
無論、研究室の他の男性諸君にも渡していたのだろう。知りたくもないが。
ふと、バルタザール・ベッカーという中世のオランダ人の言葉を思い出した。
曰く、「心は身体なしにもまた存立することができる」。
そう、あの女(ひと)の面影は、私の瞼からひとときも消えたことがない。
ああ、ファウスト博士のように悪魔と契約して人生をやり直すことが出来たら!
私は必ずや想いを伝えるだろうに……
…
……
………
「こんにちは!」
突然若い女性から声をかけられて我に返った。
「君は確か……」
「霧島マナです♪ あの、よかったら、これ、どうぞ」
なんと、たいして親しくもない私にチョコレートをくれるらしい(>>699)。
一体、これはどういう風に考えればいいのだろうか。
私と彼女の間には義理と呼べるほどの関わりすらない。
ネルフの本部内で二、三度顔を合わせたことがあるだけだ。
従って、いわゆる義理チョコではない。
もしや、極度の年上好きか? いや、よもやそれはあるまい。
しかし、見ればチョコレートは明らかに手作りであり、大きさも相当な物だ。
まさか、本当に、私のことが? しかし、いくらなんでも歳の差が………。
「あの、どうぞ。ご遠慮なさらずに」
私が受け取るのを躊躇していると、強いて勧めてくる。
その声はどこか聞き覚えが………。
ユイ君………? 君か?
瞼の中のユイ君と、目の前の少女の姿が重なる。
「すまんな、霧島君」
私は、高鳴る鼓動を抑えながら、辛うじて平静を保って礼を述べた。
「どういたしまして! さようなら、おじいさん」
――――じ、じじ、じいさん!?
おのれ……小娘が………。
どうやら、彼女は私のユイ君とはまったく違うようだ。